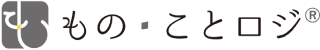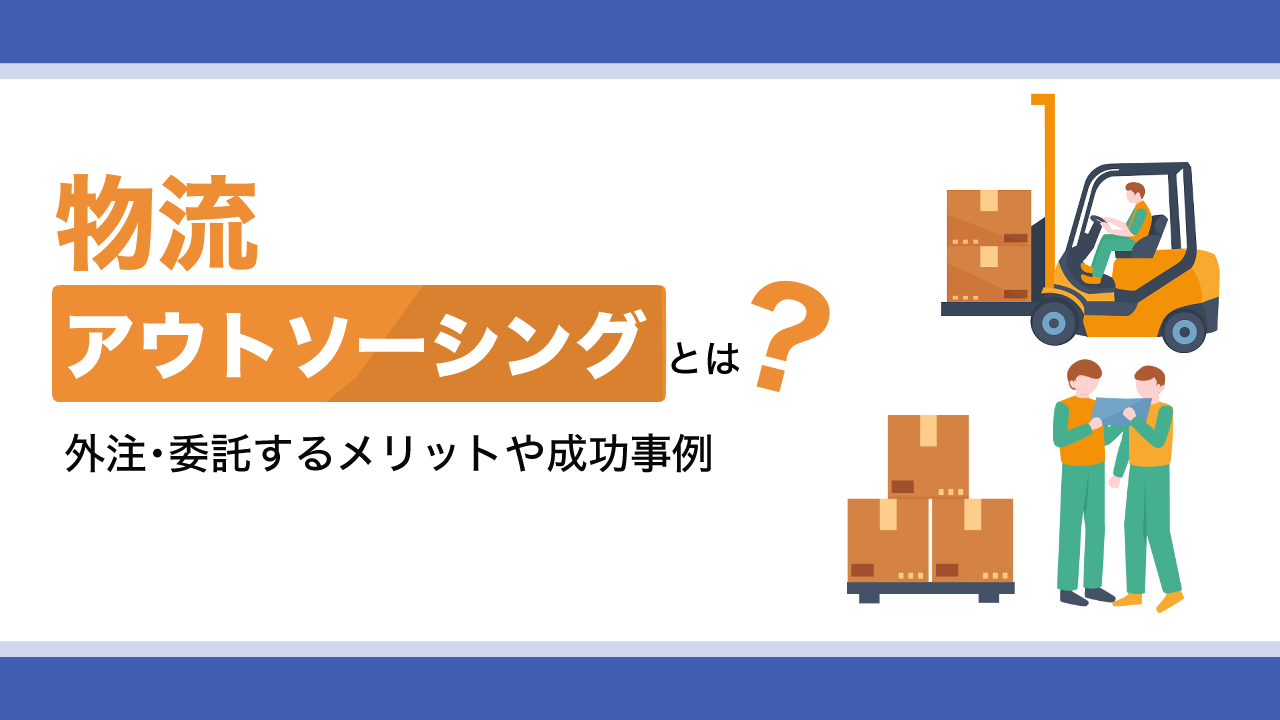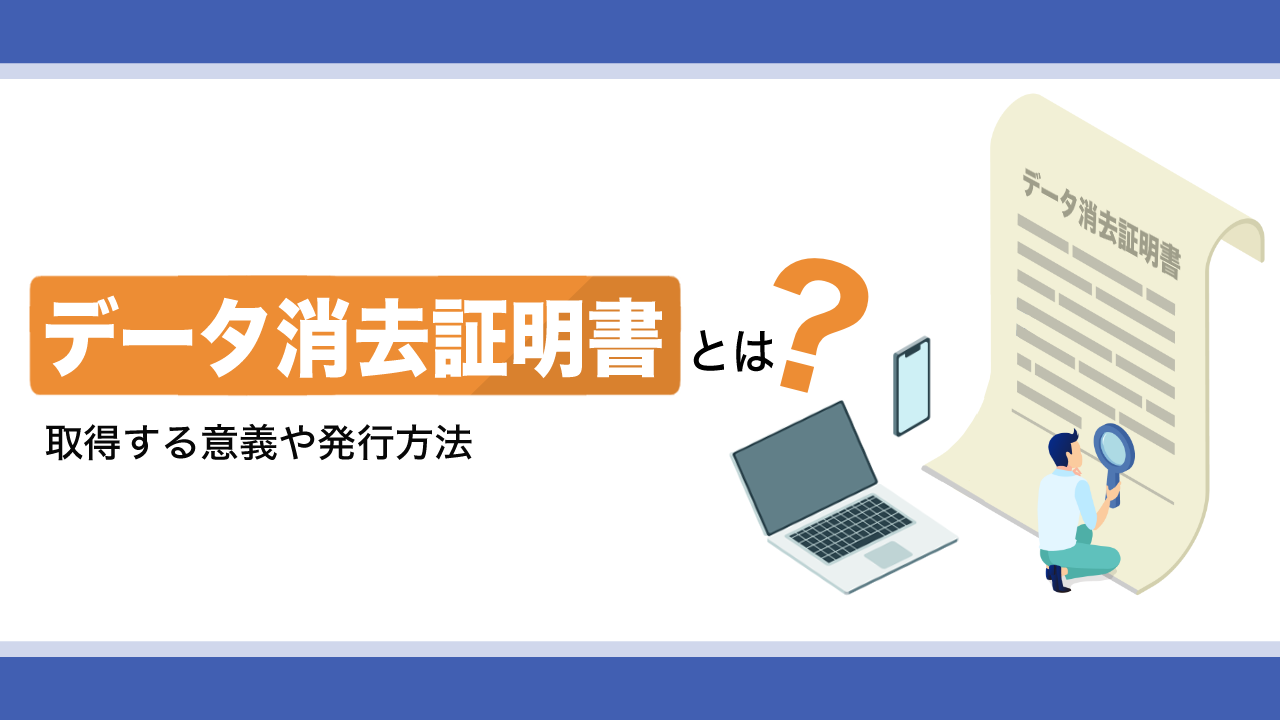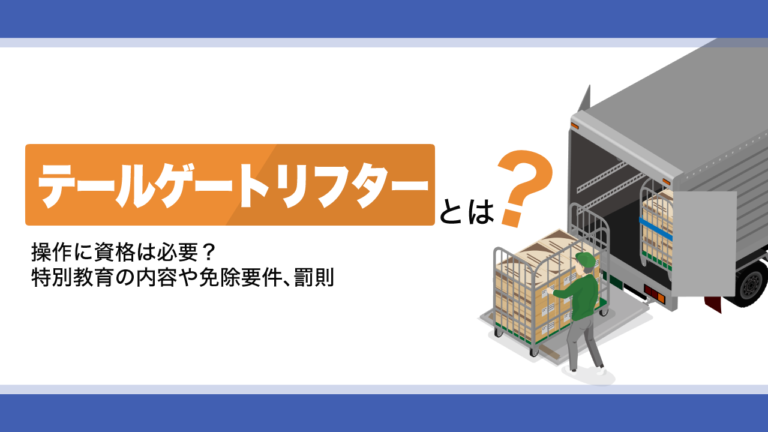物流BCPとは?策定の目的や対策事項、課題を解説

監修者プロフィール

SBフレームワークス マーケティング/広報
玉橋 丈児
物流×輸配送×テクニカルソリューションで、お客様の課題解決を目指すSBフレームワークスのマーケティング担当。テクニカルソリューション分野での実務経験を活かして、弊社のサービスや、業界の話題などを解説いたします。物流技術管理士補。
物流BCPとは、災害に対して荷主企業・物流事業者が行うべき備えや措置などを定めた計画です。物流BCPを策定して災害に対する備えや措置を決めておけば、有事の際に物流を維持、早期復旧できる可能性が高まります。
物流BCPを効果的に機能させるためには、自社の事業の実態に適した対策を講じることが重要です。
本記事では、物流BCPの策定の目的や対策事項を解説します。
自社の物流体制でお悩みの場合は、SBフレームワークスにご相談ください。30年以上にわたりソフトバンクグループの物流を支えてきた経験やノウハウを活かし、物流体制の強化をサポートします。
\豊富な実績とノウハウにもとづき提案/
目次
物流BCPとは

物流BCPとは、大規模災害などが発生した際に物流の停滞を防ぎ、物流機能を継続させるための計画です。
BCPは、「Business Continuity Plan(事業継続計画)」の略称です。自然災害やテロなどの有事の際に事業を継続、早期復旧させるための計画を指します。
物流BCPでは、このBCPの考え方を応用し、荷主・物流事業者が行うべき災害への備えや措置を策定します。一般的な災害対策とは異なり、「サプライチェーンの継続性の確保」に重点を置いている点が特徴です。
参考:国土交通省「荷主と物流事業者が連携したBCP策定のためのガイドライン」
物流においてBCPを策定する目的

物流においてBCPを策定する目的は、主に以下の2つです。
- 災害発生時における物流の維持
- 物流ネットワークの早期復旧
それぞれの内容を詳しく解説します。
参考:一般社団法人 日本物流団体連合会「物流業のBCP作成ガイドライン」
災害発生時における物流の維持
物流においてBCPを策定する大きな目的は、災害発生時に物流機能を維持するためです。
物流には、全国各地の企業や消費者に、さまざまな商品・原材料・資材などを届けるインフラとしての側面があります。そのため物流業界は、災害が起きても物流をできるだけ止めずに維持する責務を担っています。
物流BCPを策定しておけば、災害発災時に柔軟な対応が可能です。状況に応じて適切な措置を講じられ、物流の完全な停滞を防げる可能性が高まります。
さらに、支援物資輸送などの社会貢献活動に参画することで、企業の社会的信用度の向上も期待できます。
物流ネットワークの早期復旧
物流BCPの策定には、災害発生後に物流機能の早期復旧を図る目的もあります。
大規模地震や台風、豪雨などの自然災害が発生すると、道路や鉄道などの交通インフラが麻痺することが予想されます。また、停電による電力供給の停止や通信ネットワークの混雑により、物流管理システムが機能不全に陥ることもあるでしょう。
交通インフラや物流管理システムの停止により、物流ネットワークが寸断されてしまうと、物流が停滞する恐れがあります。停滞が続けば、事業の存続を揺るがす大きな損害が発生しかねません。
しかし、物流BCPを策定しておけば、代替輸送手段や緊急時のオペレーション体制に切り替えることで、物流機能の早期復旧が期待できます。
また、自社の物流機能をいち早く復旧し事業活動の停滞を最小限に抑えることで、取引先や顧客からの信頼獲得にもつながります。
物流BCPの策定において検討すべき対策事項

物流BCPの策定では、以下のような対策事項を検討する必要があります。
- 防災対策
- 発災後の対策
- 復旧対策
- 平時からの対策
物流BCPを適切に策定・実行するには、BCP策定の統括・企画を担う担当者や、BCP発動(緊急体制への移行)の判断を行う責任者を選任することが重要です。
また、BCPに対する理解を深めるために、従業員を対象としたBCPに関する教育体制を整えることも望まれます。
事業所としての対応の意思決定、意思伝達、指揮命令が迅速に行われるよう、事前に組織体制を確立しておきましょう。
ここからは、それぞれの対策事項について詳しく解説します。
参考:国土交通省「荷主と物流事業者が連携したBCP策定のためのガイドライン」
参考:一般社団法人 日本物流団体連合会「物流業のBCP作成ガイドライン」
防災対策
災害による物流へのダメージを抑え事業を継続させるためには、防災対策が必須です。平時から適切な防災対策を行っておけば、災害発生時の被害を最小限に抑えられます。
物流BCPで検討すべき防災対策は、以下などが挙げられます。
- 災害発生時の事業所や施設の被災の危険度、被害程度の予測
- 事務所や施設建物の耐震性の確認
- 倉庫内の在庫の荷崩れ対策
- 事務所や施設内の書類・備品の整理整頓
- 消火器や救急用品、避難・救難機材の準備
- 食料・飲料水・毛布の備蓄
- 業務遂行に必要な各種データの定期的なバックアップ
- 事務所や車両、倉庫などの主要施設の代替拠点・非常用設備の確保
実際に災害が発生した際の自社の物流への影響や施設の被害状況を想定して、適切な防災対策を講じましょう。
発災後の対策
発災後の対策を決めておけば、自社の物流機能を早期復旧させるための行動基準が明確になり、災害が発生した際に迅速な措置ができます。以下の項目について確認・検討しましょう。
- 避難経路や避難場所
- 発災報告の手順や災害対策本部の設置など、BCPの発動の基準
- 安否確認の手段・連絡体制の整備
- 事業所の建物や施設、車両などの被害状況を把握する担当者の選任
- 取引先や関係者への情報共有方法
- 営業所や支店への応援・支援体制の整備
- 物流倉庫の設備、商品在庫の状況を確認する担当者の選任と情報共有方法
- 道路の損壊、公共交通機関や配送業者の運行状況などの情報収集と共有方法
- 金融機関のシステムの稼働状況
- 通信インフラの稼働状況
発災後は、人命を最優先として行動する必要があります。BCPを機能させ事業を継続するためにも、従業員およびその家族の安全確保、被害状況の把握を第一に、行うべき措置を講じましょう。
復旧対策
災害発生時にできる限り早く自社の物流機能を復旧させるためには、あらかじめ復旧対策について策定することが大切です。
以下のような事項について検討し、速やかな判断ができるよう準備しておきましょう。
- 復旧する業務やサービスの優先順位
- トラックやフォークリフトなどの燃料確保の方法
- 必要な運転資金の把握
とくに重要なのが、復旧する業務やサービスの優先順位の設定です。
災害発生時は交通インフラの停止や被災状況により、平時の従業員数の確保が難しいことが想定されます。その中で、従業員や庫内スタッフの安全を最優先として復旧を進める必要があります。
安全を確保したうえで、社会的重要性と緊急性が高い業務やサービスを優先しなければなりません。以下のような優先順位で復旧を進めましょう。
- 二次被害対策(倉庫内の瓦礫、ガラス、倉庫内転倒物などの適切な処理)
- 社会的に重要性が高い業務(支援物資輸送やインフラに関わる物流など)
- 売上や利益への貢献度が高いサービス
平時からの対策
物流BCPの実効性を高めるためには、以下のように平時から対策を準備しておく必要があります。
- 物流倉庫の複数拠点化
- 有事の際の代替配送ルートの想定
- 定期的なBCP訓練の実施
- 計画の継続的な見直し
物流倉庫の複数拠点化は、物流機能の早期復旧に有用です。物流倉庫を複数の拠点に分散させておけば、災害により一つの拠点が被害を受けても、他の拠点で物流機能を継続できます。交通インフラが寸断される可能性を考慮して、代替配送ルートも検討しておきましょう。
定期的なBCP訓練の実施は、従業員が物流BCPの重要性を理解するのに効果的です。実際の災害を想定して訓練すれば、各従業員の役割や取るべき行動がわかり、BCP発動時の実効性が高まることが期待できます。
具体的には、大規模災害の発生を想定して、以下のような訓練を行うとよいでしょう。
- 電話やメール、安否確認ツールによる緊急連絡・応答の訓練
- 災害発生時の対応や復旧の役割分担の確認
また、物流BCPをより実態に則したものにするために、計画を継続的に見直すことも重要です。BCPの担当者や実行責任者を中心とした定例会議を開き、訓練などを通して明らかになった不備や最新の災害事例から改善点を検討し、BCPに落とし込みましょう。
物流BCPの課題

物流BCPは、災害発生時に事業継続の可能性を高めるために重要である一方で、運用にあたっては多くのリソースがかかる課題があります。
災害発生時に物流の停滞を防ぐには、非常用設備の準備や事業所建物の耐震性の強化などを行う必要があり、費用面で大きな負担となりがちです。
また、被災した営業所や支店の機能を補うために一時的な応援などを行う場合は、その分の人的リソースも確保する必要があります。
物流BCPを策定する際は、自社のリソースを把握したうえで自社単独で実現可能かどうかを検討することが大切です。
物流BCPの取り組みが難しい場合はアウトソーシングを検討

自社で物流BCPの取り組みができそうにない場合は、物流機能そのもののアウトシーシングを検討するとよいでしょう。自社の物流業務をアウトソーシングすれば、物流BCPの運用に必要となる設備や人員を自社で確保する必要がなくなります。
すでにBCP体制を構築している物流代行業者もあるため、アウトソーシングを選択した方が災害発生時の業務継続力が高まる可能性があります。人員の補充や代替ルートでの物流確保など、状況に応じた措置が速やかに取れることから、災害が発生した際の物流の停滞を最小限に抑えられます。
どのような災害対策設備を導入しているかを確認して、自社に適した物流代行業者を選びましょう。
物流BCPを策定して災害に強い物流ネットワークを構築しよう

物流BCPを策定しておけば、災害発生時の業務継続力の向上が可能です。物流BCPにより、有事の際も自社の物流機能を維持し続け早期に復旧できれば、サプライチェーンの継続性が高い企業として取引先からの信頼獲得も期待できます。
消費者の生活や顧客の事業を支える責務を果たすためにも、物流BCPを策定して災害に強い物流ネットワークを構築しましょう。
自社での物流BCPの取り組みが難しく、物流業務のアウトソーシングを検討している場合は、SBフレームワークスへご相談ください。弊社では、3PLと呼ばれる物流代行サービスを行っております。最適なコストで盤石な物流体制を提供いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
\豊富な実績とノウハウにもとづき提案/
監修者プロフィール

SBフレームワークス マーケティング/広報
玉橋 丈児
物流×輸配送×テクニカルソリューションで、お客様の課題解決を目指すSBフレームワークスのマーケティング担当。テクニカルソリューション分野での実務経験を活かして、弊社のサービスや、業界の話題などを解説いたします。物流技術管理士補。
関連記事
サービスの詳細について資料をご用意しております。社内での検討などにご活用ください。
サービスの詳細や料金へのご質問、商談のお申し込みや、お見積りのご相談は、こちらよりお問い合わせください。